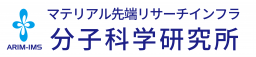2024年度ARIMデータのRDE(Research Data Express)登録完了について(お願い)
2025年4月1日
分子科学研究所 機器センター
センター長 横山 利彦
2024年度に「マテリアル先端リサーチインフラ」をご利用いただいた皆様のデータ登録期限は、
2025年5月26日(月)となっております。
これは、文科省への提出期限であり、期日を過ぎて登録しても成果には入りません。
分子研の評価が下がることは、保守点検費のための委託費用の減額につながり、一部の設備が利用停止となることも懸念されます。
共同利用機関として、利用者の皆様の利便性を確保し安定した支援を継続していくためには、利用者である皆様のご協力が不可欠です。
データの登録はやや煩雑ではございますが、登録後のメリットもございます。
・共同研究者と分析・計測データを共有できます(ストレージとして使用)
・論文雑誌に投稿時のデータリポジトリとして利用できます(アーカイブとして活用)
・データカタログにDOIが付きます(永続的なデータの利用)
※ DOIの付与につきましては、「データカタログ作成要項」の第 3 条(データカタログの記載要件)を満たすことが条件となります。
https://arim.ims.ac.jp/wp-content/uploads/20241001_DATA_Catalog.pdf
データ登録が必要な設備は、設備一覧(https://arim.ims.ac.jp/howtouse/list/)で設備IDがハイライトされている設備が対象となります。
有意なデータが出ているにもかかわらず登録されない方は、分子研のARIM支援装置の利用をお断りすることもございます。
皆様におかれましては、利用申請時に「データ登録」に同意いただいております。
データの登録は任意ではなく、義務でございますので、締切までにデータの登録をお願いいたします。
なお、データ登録作業(RDE)についての操作マニュアルをお知らせいたしますが、
ご不明な場合は、各装置担当、あるいはマテリアルスポーク事務局へお問い合わせください。
RDE(Research Data Express)操作マニュアル閲覧先:
https://drive.google.com/drive/folders/1vPMfXGkflBMspJOdQGmSxdplMtdF5L0p
各装置担当連絡先:https://arim.ims.ac.jp/contactus/
マテリアルスポーク連絡先: ims-material@ims.ac.jp
RDEについての説明:https://dice.nims.go.jp/services/RDE/#usage
簡単ではございますが、次のようにデータ登録の手順を記します。
ご協力のほどお願いいたします。
データ蓄積(登録)の手順について
データについては、マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)の代表機関である国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)のARIM事業へ蓄積(登録)いただきます。
※ 2024年度に「マテリアル先端リサーチインフラ」をご利用いただいた皆様のデータの公開は、
2027年4月1日から、となります。2年間は非公開です(特に指定がない場合)。
このような形での公開となります(https://nanonet.go.jp/data_service/arim_data.php)。
・公開期間を延長(1年)したい場合は、公開日の90日前より申請を受け付けます。
・申請書(非共用期間変更申請書_ARIM_v.1.0.docx)による、2027年1月1日以降のご申請となります。
おおまかには、次の順序で行っていただきます。
「データセットの開設」 → 「データの登録」 → 「データセットの説明等の編集」
RDE(ARIM)データ蓄積(登録)作業手順
作業0 事前準備
・Webブラウザーは「クローム」を利用(他ではうまく動作しません)
・次のアドレスからRDE操作マニュアル(分子研マニュアル)のダウンロードを行ってください
https://drive.google.com/drive/folders/1vPMfXGkflBMspJOdQGmSxdplMtdF5L0p
・マニュアル「1_RDEシステム利用手順.pdf」に記載の手順で行います。
・RDE(ARIM)のサービスをご利用になるには、「DICE」アカウント(メールアドレス)が必要です。
今回初めてARIM事業をご利用になられた方は、課題申請後に取得いただいております。
作業1 グループ作成とサブグループの作成
・どちらも分子研にて作成済みです(サブグループ名には課題番号を割り当て済みです)。
・年度ごと、申請課題ごとにサブグループは作成されます。
作業2 データセットの開設
※「2_RDEマニュアル(データセット開設・メンバ編集).pdf」をご用意ください。
① RDEのサイトを開く(https://dice.nims.go.jp/services/RDE/sitemap.html)
「データセット閲覧」へログインしますので、1-1を実行してください。
② 2.グループ詳細画面 が開きますので、3.データセットの開設 まで行います。
ご注意:データセットの開設では「テンプレート名」はv5版を選ぶ
「データ中核拠点広域シェア」にチェックしない
「データセットを匿名にする」にチェックしない
匿名化には別途申請が必要となります。チェックしないで下さい。
作業3 データの登録
※「3_RDEマニュアル(データ登録).pdf」と
「(別紙)RDEマニュアル(データ登録ファイル一覧).pdf」をご準備ください。
① RDEのサイトを開く(https://dice.nims.go.jp/services/RDE/sitemap.html)
「データ登録(ARIM事業)」へログインしますので、1-1を実行してください。
② 2.データセットの選択 画面が開きますので、一覧からデータ登録を行うデータセットを
選んでください。
③ 3.データ登録 を行います
・試料情報の記入
「試料名(ローカルID)」の他、材料が適切に同定できる情報として「化学式・組成式・分子式」、「試料の説明」
の記載をお願いいたします。データセットの品質向上にご協力ください。
・設備データ(登録ファイル形式)の確認
「(別紙)RDEマニュアル(データ登録ファイル一覧).pdf」を参照
例えば、質量分析 MALD-TOF では、
「.zip ファイル(Bruker 出力方式である質量分析データフォルダーを zip化)」して登録します。
・データ登録の開始
※ NIMS側の通信容量が小さいので、時間がかかる場合があります。その場合、ブラウザーのタイムアウトにより
エラー表示されることがありますが、「データエントリステータス」がACCEPTEDになっていればその時点で登録
作業は開始されております。
④ 4.データ登録状況詳細および一覧 にて登録状態の確認をしてください。
※ 登録するデータについて
・ARIMが蓄積するデータは多岐にわたり、すべてのデータに価値があると考えています。また、失敗データや利用者に
とって価値がないと判断したデータもご登録いただくことを推奨しています。
・原則全件登録
・ARIMの共用機器をご利用の際は、測定データ/装置データを原則として全件登録にご協力ください。
・失敗データ・期待外れデータの登録推奨
・明らかな測定ミス、装置制御の設定ミス、装置の誤動作等によるデータ、データ利用者にとって意味のない、
あるいは誤解を生じるデータは登録不要です。
詳細は「ARIMデータ登録・データ共用ポリシー」をご参照ください。
https://arim.ims.ac.jp/wp-content/uploads/Data-Registration-and-Sharing-Policy.pdf
作業4 データセットの説明等の編集
登録いただいたデータセットからデータカタログを作成するにあたり、必要な記載事項は次の4つです。
・データセット名
・データセットの説明
・材料・マテリアルに関する情報
・データセット管理者
上記4項目の詳細、編集方法については、「ARIM データカタログ公開ポリシー」をご参照ください。
https://nanonet.go.jp/data_service/page/data_catalog_policy.html
ご不明な点は、各装置担当、あるいはマテリアルスポーク事務局へお問い合わせください。
・各装置担当連絡先:https://arim.ims.ac.jp/contactus/
・マテリアルスポーク事務局連絡先: ims-material@ims.ac.jp
本件のお問い合わせ先:
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38
自然科学研究機構分子科学研究所
機器センター マテリアルスポーク
TEL:0564-55-7431 FAX:0564-55-7448
E-mail:ims-material@ims.ac.jp